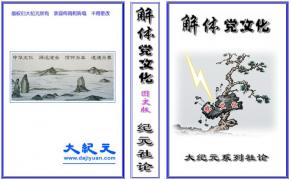|
評論 > 評論
引用サイト:大紀元
https://www.epochtimes.jp/jp/2008/06/html/d89599.html
【党文化の解体】第2章(14)「政治闘争の中での洗脳教育」
3-2)政治闘争の中での洗脳教育
中共は闘争哲学に頼って政権を奪った後も、この哲学で統治を維持してきた。中共が次々に発動した政治闘争の中で、国民の闘争の思想は次第に強化された。その結果、もともと中庸の道を尊重し、和を大切にしてきた中華民族は、闘争を日常生活の一部分と見なし、人と人との間に満ちた不信感を社会常態と見なし、人々の間の争い、騙しあいを競争社会での生存手段と見なすようになった。 1951年、中共は政権を樹立して間もなく、足元を固めたばかりにもかかわらず、すぐ知識人に対する「思想改造」の運動を始めた。映画『武訓伝』に対する批判は、この運動の幕開けとなった。この運動はほぼ毛沢東の望み通り、知識人の思想を改造する目的を達した。 これをきっかけに、中国人の考え方は大きく変化し、「階級闘争」のみが善悪を量る唯一の基準だと思うようになった。清朝末期に生活していた武訓は、貧しい家庭の子弟が教育を受けられるようにするために、乞食をして得たお金で学校を作り、様々な屈辱を嘗め尽くし、清貧な生活を送っていた。しかし、彼は「封建社会の経済基礎とその政治構造を壊そうとせず、かえって封建文化を熱狂的に宣伝していた」(毛沢東の言葉)として、階級の立場を間違えたということで、中共から嵐のように攻撃された。 もう一人の歴史人物、明の時代の海瑞は権力を恐れず、公平に法律を執行し、清廉潔白で人々から敬愛されていたが、中共から見れば、海瑞は「搾取階級」に属し、「地主階級の利益を守っていた」から、庶民のために行った全ての良いことがいずれも、「統治階級を守るため」だと決め付けられ、文革の初期から強烈に批判された。 さらに、国民政府が南京市で建てた「航空烈士共同墓地」に抗日戦争で亡くなった全国各地の100名以上の空軍烈士および、戦争の中で中国のために命を捧げた米軍教官、旧ソ連のパイロットらが埋葬されていた。これに対して中共は、彼らは「反動政府」のために働いたと決め付けて、文化大革命が始まってまもなく、毛沢東の紅衛兵は墓地を潰して、烈士らの遺骨は全部捨てられた。 共産党は、闘争性は即ち革命性だと認識しており、対立と衝突は悪いことではなく、良いこととされてきた。なぜならば、これは「革命の種」だからである。歴史は闘争の中で前進してきたと考えている。(しかし、今日の中共は革命という言葉が使われることを恐れている)。しかし、闘争性は人間の先天的本性ではないため、共産党は人々の「革命の意識」を啓発する必要があり、絶えず「教育」を施し、革命の意識を高めなければならないと考えた。そのために、詐欺の手段で故意に対立と衝突を作り上げることも辞さなかった。 例えば、共産党の革命理論を宣伝するために創られた舞台劇『白毛女』の主人公はもともと、民間伝説では善い人を見守り、悪人を戒める仙女であったが、中共は国民を洗脳教育するために、この伝説の仙女を「搾取階級」に苦しめられた貧困階級のモデルに仕立てあげた。劇中で「千年の仇を討ち、万年の冤を晴らす」と復讐を煽り、あまりの煽動力で、劇中で悪役の代表を演じていた役者が劇を見ていた兵士に銃撃された一幕もあるほどだった。 いわゆる「階級意識の啓蒙」、「階級感情の育成」などは、実際、人々に闘争の思想を叩き込んで、復讐の論理を教え込むことである。以前、中共は「血で血を洗う」、「憎しみを心に刻む」、「苦しみを肝に銘じ、階級の仇を忘れぬ」などと宣伝していた。 ところが、改革開放が進むにつれ、文明社会に唾棄されたこのような宣伝は赤裸々に行うことができなくなった。以前のように「昔の苦しみを思い起こして、今の幸せを噛み締める」という宣伝をしなくなったが、やり方を変えて、現代科学の技術を駆使して、このような宣伝を引き続き踏襲している。 例をあげると、中共は法輪功学習者を迫害し、人々の法輪功に対する憎悪の念を煽るため、自作自演で「天安門焼身自殺」をでっち上げた。国際教育発展組織(International Educational Development)は2001年8月14日、この茶番劇が嘘偽りのものだと正式な声明を発表した。 中共の歴史上のさまざまな政治運動や各種の洗脳方式の宣伝により、人々は知らず知らずのうちに、共産党に決め付けられた「敵」に対して、骨髄に徹するほどの恨みを抱くようになった。これらの「敵」とは、「地主」、「資本家」、「富農」、「反革命分子」、「右派」、「走資派」、「民主運動活動家」、「邪教分子」等などである。 そして、革命意識の高さは、これらの「敵」への恨みの深さによって評価される。中共は人々に「雷鋒の精神を学び、敵に対して厳冬のように冷酷無情でなければならない」と教え、このような「階級感情」が、人類の全ての感情を凌駕していると教えてきた。 毛沢東いわく、「人を暴行する行為についても階級の概念から分析しなければならない。悪い人が良い人に暴行されたなら、これは自業自得と言い、良い人が悪い人に暴行されたなら、良い人にとって名誉なことであり、良い人が良い人に暴行されたなら、これは誤解によることだ」。この話は文革のとき、「紅衛兵」の中で広く知られていた。階級の敵が暴行されても、それは彼らの自業自得であるとされたため、暴力と流血は瞬く間に中国の地に広がった。 革命者らの階級感情からすると、当時、国家主席であった劉少奇は、人民の「救いの神」(毛沢東)に反対した以上、死んでも罪を償うことができない。張志新は、劉少奇の肩をもつ以上、看守所で集団レイプされても、喉を切られて銃殺されても、当然のことである。雷鋒の「敵に対して冷酷無情であるべし」はここで如実に現れている。 文革初期に起きた紅衛兵らの蛮行として名高い「紅八月」の赤色テロで、教え子に殴られ死んでしまった教師らは少なくなかった。彼らは教え子に党の要求通りに「敵に対して厳冬のように冷酷無情であるべし」、「鞭を取って敵を打とう」と教えたことが、後に自らの死を招くとは思いもよらなかったであろう。 批判闘争会のとき、参加者の誰もがわれ先にと自分の階級性をアピールしていた。敵に対する恨みが深ければ深いほど、愛憎の念が明白で、階級意識が高いと思われる。でなければ、「階級的立場がしっかりしていない」という恐ろしい疑いがかけられてしまう。 もし、家族の一員が「党の敵」と指定されたら、家族全員が必ず、立場を表明し、その一員と一線を画さなければならない。反右派闘争のとき、中国民主党派のリーダーであった章伯鈞が「最大の右派」と指定された後、その息子と妹は相次いで、新聞に彼を批判する文章を発表した。また、毛沢東自らによって右派のレッテルを貼られた儲安平(章伯鈞の友人で、『光明日報』の編集長であった)の息子は父親に次の言葉を送った。「儲安平に忠告しておきたいが、破滅する前に心を入れ替え、人民の意見を真摯に受け止め、反社会主義という考えの根源を掘り出し、自分の問題を隠さずさらけ出しなさい。このままいくと、死をもって人民に謝罪するしかない」。 人々は次々にやってきた政治闘争の中で、次第に闘争の思想を注ぎ込まれた。このような「霊魂に触れる」闘争の中で生き残るために、人々は冷酷無情に自分の良識を包み隠す処世術を覚えた。相手を攻撃し苦しめてはじめて、自分の安全を守ることができると思うようになった。そのため、多くの人は「弱肉強食、適者生存」が現実的な生活法則だと考えるようになった。 中共に上演を禁じられた映画「青い凧」の中に、実生活に基づいたシーンがあった。反右派闘争が始まった後、主人公の父・林少龍の勤め先では一人の右派を指定するように党組織から命じられた。この右派を誰にするか、皆で会議を開いた。決まらないと散会できない。林少龍はこの肝心な時、トイレに行くために席を離れた。会議よりトイレのほうが大事だと思ったのだろう。席に戻ったら、彼は既に右派として「推薦」されていた。 「生きるか死ぬか」の政治闘争の中で、人々は道徳の最低限も守れず、他人を踏みにじることによって、自己保全を図るという「厚黒術」(厚かましくかつ腹黒く生きよという処世術)を身につけた。今日になって、同様に常に「生きるか死ぬか」の危機に晒されている現代社会のビジネス戦争の中で、利益のために横領や汚職、品質粗悪商品、ニセモノなど、憚ることなく相手の利益を損なう行為が横行するのも不思議ではない。そこに依拠する哲学はいずれも、「弱肉強食、適者生存」である。 今日、人々は「成功」できるかどうかを、個人の価値を量る唯一の基準としている。しかし、その成功の手段は問題視されていない。金持ちに寄り添うことは女性の目標であり、美人に囲まれることは男性の見栄であり、子を一流大学に進学させるのは親の唯一の望みである。この闘争の哲学を下敷きとする「成功」は、人の失敗を願い、良識と公徳心もなければ、是非と善悪もない。勝てば「官軍」、負ければ「賊軍」。 そのため、自分の事業を「成功」させるために、労働者を奴隷のように扱う工場が溢れて、出稼ぎ者は人間らしい扱いを受けられず、有毒の商品、粗悪質の商品が市場に溢れている。「金持ちに仁義なし」という論理は至極当然のことだと考えられている。権力を弄んで罪を犯しても処罰されない人は、「後ろ盾のある人物」だと思われている。 「弱肉強食、適者生存」という党文化に影響され、中国人は争い合うことに熱中し、誰に対しても疑心暗鬼になり、社会全体の結束力を失った。結束力のない人々は中共の極権政治にとって好都合のものである。 |